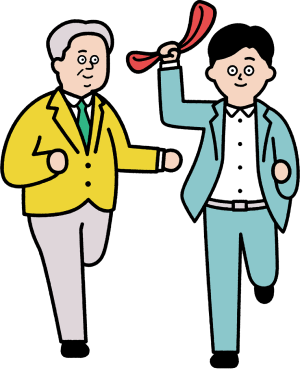東京・神田淡路町、オフィス街のど真ん中にある「近江屋洋菓子店」。ショートケーキやアップルパイが人気の洋菓子店です。
2021年5月に改装工事のため休業した際には、営業最終日に2軒先のビルまでお客さんが並んだほど。リニューアル後もお店にはたくさんのお客さんが訪れています。SNSには「変わらずに美味しい」「昭和レトロな内装はそのままで嬉しい」「喫茶コーナーの再開が待ち遠しい」といった声がたくさんアップされています。
現在、この店を経営しているのは、5代目・吉田由史明(よしあき)さんです。「リーズナブルだけどチープでないものを」という理念を掲げ、多くの人に愛され続けてきた老舗を、27歳の若さで父・太郎さんから引き継ぎました。
時代の変化や家業の伝統など、様々なものに対して「自由は不自由の中にある」と考え、お店を運営する吉田さんからお話を伺いました。
「地域に根付いたお店はいいものだな」

130年以上続く洋菓子店の息子として生まれた吉田さん。幼少期から家業を継ぐことを意識していたそうです。
吉田さん「ずっと父の背中を見ていて憧れていました。大学に進学しそろそろ就活…となった20歳の時、『この業界で仕事をさせてほしい』と申し出ました。その時点では承継の約束はありません。『形にならなかったら継がせない』と言われましたので。大学卒業後、東京と岡山の洋菓子店で修行を積み、スペインにも留学し、帰国後に店に入ることになりました」
当時、先代はまだ65歳。継承にはまだ早いようにも思えますが、先代には「そろそろ息子に引き継ぎたい」という気持ちがあったと言います。

吉田さん「僕が生まれる前、祖父が62歳で急逝し父は26歳の若さで急遽継ぐことになったんです。あまりに急だったので当時はつらかったと思います。その経験も踏まえて、自分は元気なうちに引き継いで状況を整えてくれたようです。そういったことも含めて尊敬していますし、感謝しています」
近江屋洋菓子店の周りには蕎麦屋さんや鰻屋さんなど長年親族で経営しているお店がたくさんあり、周囲の人は僕が店を継ぐだろうと思っていたようですね。そのことに多少抵抗を感じた時期がないわけではありませんが、父は『絶対に継げ』とは一言も言わず、いつも『継ぎたくなければ継がなくていい』と言っていたので、それほど気になりませんでした。
今思えば、周りのみなさんの思いはあたたかく迎えてくれる気持ちの表れですし、そうした環境の影響を受けて、僕も『地域に根付いたお店はいいものだな』と思うようになっていきました」
ケーキが時代に合わなくなれば、違うものを販売するかもしれない

近江屋洋菓子店の創業は明治17(1884)年。当初は炭屋でした。しかし夏は炭が売れなかったことからパンを売るようになります。ほかにも当時流行っていたカリン糖やドラ焼きなどを並べ、原料の砂糖も販売。その後、明治28(1895)年、2代目・菊太郎さんがアメリカに渡ってケーキを学び、3代目、4代目、そして5代目の吉田さんへ受け継がれます。
吉田さん「炭屋からパン屋になったように、ケーキが時代に合わないということになれば、また違うものを販売する可能性はあります。時代の変化とともに人も変わる。その時代に合わせた商品をご提供していったほうがいい。それは父から教わってきたことです。
実際、僕らの商品もずっと昔から作り続けているというものは少ないんです。人気のあるショートケーキ、アップルパイ、フルーツポンチ、レーズンビスクィも先代がつくりました。
その前からあるのはソフトクリームくらいじゃないかな。洋菓子は常にキラキラしたものでありたい。新しいものにすぐに飛びつくというわけではありませんが、時流を見ながら商品を変えていくことに抵抗はありません」

ケーキをイヤイヤ買いに来る方はいない
変わっていくことを悲しむ客もいますが、そこに「納得してくださる方も多い」と語る吉田さん。変えることを恐れないのは、従業員の働きやすさを考えてのことでもあります。
吉田さん「昔のケーキのレシピは手作業が前提。作業にかなり時間がかかり、職人が帰れなくなってしまう。昔は休む間もなく働くことが美徳だったかもしれませんが、現代の働き方には合わない。もちろん手を抜くわけではありませんが、機械でできる部分は機械で行います。
僕らにとってお客様も大切ですが、従業員も大切。残していくべきものと変えるべきもの、優先順位を決めて選んでいかないとならないと考えています」
テレワークが進み、対面での商談が減ったため、焼き菓子など法人用ギフトの需要が激減してしまった新型コロナウイルスの感染拡大に対しても、取捨選択をして適応しています。

吉田さん「核家族や独身者が増えたことで、ここ20年ほどホールケーキの売り上げが減っていたのですが、コロナ禍でホールケーキを買っておうち時間を楽しみたいという方が増えました。コロナ禍のストレスを解消したいとケーキを買いにきてくださる方も多い。
ケーキって、イヤイヤ買いに来る方はいないんです。つらいときでも、甘いものを食べれば少しは気持ちが晴れるかもしれない。楽しいときに食べるともっと楽しい。人の笑顔にいちばん近い仕事だと思っています」
ニューノーマル時代のおうち需要に合わせて、高級フルーツをふんだんに使ったタルトや郵送できるケーキなどの商品を新たに開発。「時代に合わせて商品を変えていく」という、初代の近江屋洋菓子店イズムが今も生きています。
商品がショーケースから無くならないように。お客さんにワクワク、ドキドキを届けたい
 写真撮影:ENO
写真撮影:ENO
機械を使い、従業員が余裕を持って商品を作ることは、ひいてはお客様のためにもなります。
吉田さん「ケーキは生活必需品ではなく嗜好品。たくさんの中から選べるというワクワク、ドキドキ感が大事だと思っているんです。だから、繁忙期にショーケースが全部なくなってしまうことは避けたい。
2017年、本郷店を閉業した時にたくさんのお客様に並んでいただいたのですが、商品が切れてしまいご希望の商品を買っていただけませんでした。できる限り多くのお客様にご希望の商品をお届けしたい。クオリティを維持できる範囲で大量生産するためにも機械を入れています」
今回、改築休業前の最後の営業日にも、顧客が2軒先のビルのところまで並んだそうです。それでも最後まで商品を切らすことなく、吉田さんは「結果を出せた」と振り返ります。
 写真撮影:ENO
写真撮影:ENO
吉田さん「ただ、それが経営者として正しかったかどうかはちょっとわからないですね。残ったらロスになるわけですから。もちろん捨てずに、営業終了後、お世話になった方々に『もしよかったら』とお配りしました」
先代は吉田さんに判断を委ねる形で、閉店間際の様子は見ていないそうです。商品が残ったことについては特に何も言われなかったとのこと。「何も言われなかったということは、ある程度満足してもらえたのかな」と吉田さんは捉えています。
不自由の中の自由をみつけて成長させることが楽しい
長い歴史を受け継ぐことは「やりたいことが自由にできない」と考える人もいるかもしれません。しかし、吉田さんは「たとえ独立しても完全に自由ではありません。資金、設備、従業員……思うようにいかないということは絶対につきまとうはず」と考えます。
 写真撮影:ENO
写真撮影:ENO
吉田さん「自由は不自由の中にあると思うんです。一見、不自由に見えても、その中から自由をみつけて成長させていくことが僕は楽しい。今までも時代の流れや外部の環境など、お店を続けていくにあたって”不自由なこと”はたくさんありました。だけど、その中にも必ず自由はありますし、不自由の中の自由にこそチャンスがあるのではないでしょうか。
僕が店に初めて入った日、喫茶に入られたお客様がメッセージが残してくださったんです。『昔、父によく連れられて来ました。今日は私の子どもと一緒に来ました。嬉しかったです』と。お客様に愛されていると実感しましたね。長い歴史を含めて譲っていただいたことに責任を感じつつも、幸運なことだと思っています」
実は今回、吉田さんの顔写真を公開しなかったのも近江屋イズムの表れ。
吉田さん「次の後継者がスムーズに承継できるよう、自分個人よりも店を前面に出していきたい」
こうして近江屋洋菓子店のエッセンスは代々受け継がれ、変わらずに進化を続けています。
文:安楽由紀子